花火の色とLED 電子の基底情痴と励起状態
電子が励起状態から基底状態に戻るときに光を出す
江戸時代の花火は燃焼温度が低い黒色を使っていたため、赤っぽくて暗い花火のはずですが、時代劇「水戸黄門」では青い花火が生まれています。
うろ覚えですが、高橋元太郎さんが演じるうっかり八兵衛が火薬の中にうっかり銅の錆を入れてしまった失敗から生まれました。
この錆は緑青(塩基性炭酸銅)と言われ、お寺の銅葺き屋根にはよく見られ、昔は有毒と言われていましたが、現在は毒性はないと言われているものです。
金属を無色の炎で熱して高温にすると、その金属特有の色を発します。
これは、金属原子内の電子が熱せられることによってエネルギーを得るので高い位置に行きますが、 励起状態という不安定な状態なので元の位置の基底状態に戻ります。
励起状態から基底状態に戻るとき余分なにエネルギーを光として放出します(目で見える波長域なら可視光として感じます)。
このときに放出される光の波長(色)はその光が捨てるエネルギーの大きさと関連しているので、 捨てるエネルギーの大きさで放つ色が決まります。
そして、電子が捨てるエネルギーの大きさは、励起状態と基底状態の差で、この差は原子によって決まっていますから、 逆に言えば、原子によって放つ光の色が決まっているわけです。
熱した金属から色のある光が出ることを炎色反応と呼びます。
電気配線用銅線を調理用ガスコンロで熱して現れた炎色反応の写真です。手持ちのスローシャッタなのでボケています。
輝線スペクトルと吸収スペクトル
白熱電球が出す光を分光器でスペクトルを見ると下図のように赤から紫までの連続スペクトルになります。
ところが、電子が励起状態から基底状態に戻るときに発する光は波長が決まっているので、その光を分光器を通してみると下図の様にその波長の部分だけが明るく見えます。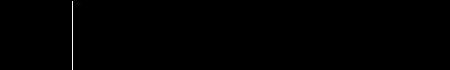
白い線がスペクトルの輝線です。
分光器を覗く機会はめったに無いと思いますが、電子が励起状態から基底状態に戻るときには特定の波長の光しか出さないことは、 同じ原理で光を出すLED照明(発光ダイオード)を使ったイルミネーションや信号機を見れば解ると思います。
イルミネーションや信号機にLEDが使われる前は電球のガラス部分に色を付けたものでしたので付けた色以外の光が漏れてすっきりとした感じがありませんでしたが、 LEDは特定の波長の光しか出さないので鮮やかに感じます。
LEDが特定の波長しか出さないことはLED照明には虫があまり寄って来ないことでも解ります。
白色LEDは、紫外線を出し、紫外線を白色蛍光塗料に当てて白色光を出しているのですが、 特定の波長の紫外線しか出さないので虫があまり寄って来ないのです。
今度は、逆に、白熱電球の様に連続スペクトルを持つ光が電子にエネルギーを与えて電子が基底状態から励起状態になったときには、 下図の様に電子に吸収された波長の部分だけ暗くなります。
これが吸収スペクトル(暗線)です。暗線の波長が判れば吸収した元素の種類が判ります。
花火に使われる主な炎色反応の例
- 赤色は、硝酸ストロンチウムなどのストロンチウム化合物
- 緑色は、硝酸バリウムなどのバリウム化合物
- 黄色は、シュウ酸ナトリウムなどのナトリウム化合物
ただし、塩化ナトリウム(塩)は空気中の水分を吸収して湿気るので使えません - 青色は、硫酸銅などの銅の化合物
しかし、青色発光ダイオードの開発が遅れたように、青色は高温にしないと出ないので花火で青色を出すのも難しいようです。